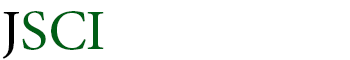「事業承継」は、「経営(社長)の承継」と「会社所有権(オーナー)の承継」を包括する概念ですので、未上場ファミリー企業の事業承継のあり方はさまざまです。それは、その会社の創業からの発展の歴史、直系身内後継者の存在の有無、株主構成、同族株主間の関係、業種、業績、企業規模など多くの要因によって変わるものだからです。
(多い類型)
所有と経営が実質的には分離しない形態です。
①スタンダード型
最も多いのは、オーナーの持ち株をその子息が引き継ぎ経営も引き継ぐというものですが、最近ではこの形は必ずしも大多数ではありません。その理由としては、子供の数が少なくなっている当節では、オーナーは必ずしも子息に恵まれませんし、恵まれていたとしても当の子息が積極的に引き受けるとは限らない、また適任・適齢とは限らないという事情などがあるためです。
②準スタンダード型
次いで多いのは、経営は娘婿に引き継がせて、株式は実の娘中心に引き継がせるというものです。これは厳密に見ると所有と経営が分離していますが、夫婦であり、孫が成長すれば将来再び所有と経営が合一するというわけですから、準スタンダードと言えます(時々、離婚により根本的に崩壊する事例が見られます)。
(もう一つの類型)
直系の身内でない人が経営にあたる(社長になる)、いわゆる所有と経営が分離する場合です。
(当社団法人は、この類型の会社を事業対象にします。)
③傍系の同族型
オーナーと共に、あるいはオーナーに使われるかたちで一緒に仕事をしてきたオーナーの兄弟、義兄弟、つまり傍系の身内が経営執行面を引き継ぐ場合です。元オーナーの遺された夫人は「お義姉さん」、息女は「姪っ子」となります。一緒に仕事をしてきただけに実務面に明るいので、従業員等にするとこれまで通りのように従いやすいうえに、本人は、同族故に株式問題などでも同族の間で発言しやすいということで、会社内外から頼られます。それだけに、所有と経営の分離が曖昧になってしまい、元オーナーの遺族は封じ込められることが多くなります。この型は最もトラブルが生じやすいと言えます。
④所有と経営の分離型
最近増加してきているのが、生え抜きの幹部に経営だけを委ねる事例です。いわゆる所有と経営の分離になりますが、次の二つのパターンに分かれます。
(イ)従来の、所有と経営の分離
会社の組織形態に変更を加えず、社長のポストだけを他人に任せて、株式による会社支配権はオーナー家族(遺族)で維持するやり方。
(ロ)新しい、所有と経営の分離(手放さない分岐承継)
これまでの会社を組織再編(会社分割など)し、従来事業を行う事業会社とそれを完全支配し管理する純粋持株会社(ファミリーホールディングス)に分けるやり方。生え抜き幹部などの他人に事業会社の経営を完全に任せて、オーナー家族(遺族)はファミリーホールディングス経営だけにあたる形態で、当社では「手放さない分岐承継」と名付けています。
後継社長が直系身内でない場合(上記の③と④の(イ))に起こる問題
企業のオーナーが年齢的理由や病気・事故などでリタイヤしたとき、オーナー自身に配偶者はいるが子がいない、あるいは子はいるがまだ幼い、未成年などで経営を託すには不適任などの事情により直系の身内に後を託せない場合、最終的な判断は別にしても、当面は時間つなぎ(ワンポイントリリーフ)という意味で、会社経営は傍系の同族や子飼い幹部などに任すことになります。つまり、所有と経営が分離することになります。
この場合、人選が当を得たものであれば会社経営そのものはうまくいきます。 しかし、会社支配権という側面では次のようなケースに至ることが少なからずあります。
よく見られるケース
その任された人が経営し年月を経るうちに、
①従業員持株会など経営陣が実質的に議決権を持つような第三者への割り当て増資
②他社との資本提携増資
③新株予約権の発行(行使)
④自己株取得並びにその処分・・・
などの方法により株主構成に改変を加えて、オーナー同族の持っていた会社支配権(議決権の過半を所有)を奪ってしまう。そして、新しいオーナーによる経営となる。
(注)会社存続のために真に必要な増資もあります。また、その経営トップが極めて有能で、その手腕により経営難に陥っていた会社を立派な会社にしたケースでは経営権の移行は当然です。それらと区別して考える必要があります。
このケースは、オーナーの残した遺族(夫人、子女、未成年者など)が、企業というものについての知識、経営状態についての判断力、株式議決権など会社法の規定についての知識を殆ど持ち合わせず、しかも本当に親身になってくれる相談相手がいないために経営陣のすることをずるずると是認してしまうことで起こります。 特に傍系の同族に経営を任せている場合、同族であるが故に難しい問題に発展することもしばしばあります。
「手放さない分岐承継」(上記④の(ロ))での留意点
この会社を二つに分けて「分岐承継」するやり方は、会社法での組織再編法制の整備、税法での税制適格概念の整備などで可能になった新しい形態です。
このやり方に従えば、前記③、③の(イ)のケースで起こる問題はなく、税務負担もなく実施できるうえ将来元通りの単一の会社に合併することも容易ですので、実行に踏み切りやすいと言えます。
ただし、この形態を採用してファミリーホールディングス(FHD)を設定しても、設定しただけでは持ち株会社としてのグループ経営統括機能を果たすことはできません。FHDの経営にあたるオーナー遺族(夫人・子女)はどうしても会社経営に疎いので、しっかりと他者からのサポートを受けて経営判断をする必要があるのです。また、その他者は、ありがちなバイアスを避けるために子会社である事業会社と契約関係にある関係者(専門士業)とは別の機関、人であることが必須です。
非同族会社にも起こる可能性
非同族会社でも、同様の問題はおこります。かなり前から非同族会社であった会社だけでなく、次のようなケースさえ起こります。
非同族会社で起こる極端なケース
このようなケースでは、社内の役員や社員の間では、「おかしなことだ、いつから我が社は○○家のものになったのだ!」と不満が充満します。またそれらの人は法律・会計の知識も十分ありますから対抗できるはずですが、どの人も自身の保身(雇用・出世)のことを考えるので、その時の社長のすることには誰も異議を申し立てないということでこのような結果になります。(太閤秀吉没後、家康の企てる掟破りに秀吉子飼いの奉行達は沈黙しました。石田三成だけが異議を唱えましたが、戦いのあと主家も自身も破滅しました。)